禁酒&断酒が難しい「アルコール依存症」と「脳とアルコールの関係性」とは?
日本では、「アルコール依存症」と考えられる患者数が200〜300万人いるとも言われています。そのうち、治療を受診している人数は年間約1万人程度と少数派です。お酒を飲むことで、心が開放的になれたり、リラックスすることができますが、脳が無意識にアルコールを欲してしまう「アルコール依存症」に十分注意する必要があります。そこで、「脳とアルコールの関係」を明らかにしていきます。
お酒を飲んだ脳は暴走する?!
◆ アルコールが幸せホルモン「ドーパミン」を後押し?
お酒を飲んで楽しくなるのは、お酒に含まれるアルコールによって、脳の中で「楽しい」や「嬉しい」という幸せホルモン「ドーパミン」の分泌が促されるからです。
神経伝達物質である「ドーパミン」は、中脳の腹側被蓋野(ふくそくひがいや)という場所の「ドーパミン細胞」から放出されます。そのドーパミンは、側坐核(そくざかく)と呼ばれる部位を経由して、各所に放出されて行きます。
お酒を飲んでアルコールを摂取することで、「ドーパミン」が放出されて、気持ちいい状態になり、そのメカニズムを脳が記憶していきます。
◆ 「もっと飲みたい」を加速させるのも「ドーパミン」?!
実は脳には、同じ行動をしていると満足度が逓減していく『可塑性(かそせい)』と呼ばれる性質があります。この可塑性に、ドーパミンも関わっているとされ、同じ量のアルコールを飲んだとしても、以前よりも満足できなくなってしまいます。
そして、より多くのお酒を飲んでしまうのです。その結果、二日酔いに…。それでも、また飲みたいと思うのはなぜでしょうか?
これは、「無意識な記憶」が関わっています。どういうことかというと、アルコールを摂取することで腹側被蓋野のドーパミン細胞からドーパミンを放出することを脳自体が記憶しているからです。そのため、「アルコール」を感じると脳は、「報酬」と感じ取り、飲み続けてしまいます。
◆ アルコールがリラックスホルモン「GABA」を模倣する
日本では、チョコレートの名前にもなっている「GABA」。このGABAは、気持ちをリラックスさせる「抗ストレス作用」があります。このGABAをアルコールが模倣することで、リラックス効果が生まれます。
ですので、お酒を飲むとリラックスするんですね。
◆ リラックスホルモン「セロトニン」の分泌も
ストレスホルモンである副腎皮質から分泌される「コルチゾール」や「ノルアドレナリン 」などの分泌を抑える「セロトニン」も分泌されるので、よりリラックス度合いが高まります。
このように、「楽しい」や「嬉しい」というポジティブな気持ちを促してくれつつ、ストレスを抑えてくれるホルモンを分泌してくれることで、楽しい気持ちになり、よりリラックスすることができます。
この状態を脳をはじめとする体が覚えていることで、「お酒」が欲しくなってしまい、それが過剰になると「アルコール中毒」や「アルコール依存症」になるリスクが高まってしまいます。
では、アルコール中毒やアルコール依存症になりやすい人にはどんな特徴があるのでしょうか?

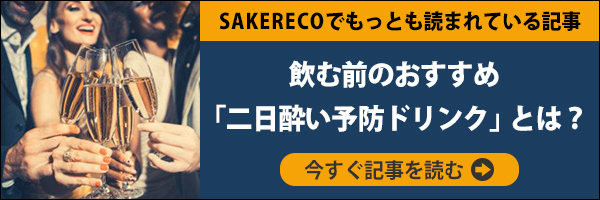







コメントする